2025年参院選で最大3.13倍となった一票の格差。 なぜ北海道の票の価値が低いのか?選挙制度の矛盾や都市と地方の代表制について、北海道を例にわかりやすく解説します。
目次
- なぜ選挙後に一票の格差が話題になるのか?
- 「一票の格差」の象徴としての北海道
- 北海道の票はなぜ「軽い」のか?
- 北海道選挙区に見る制度の矛盾
- 今後どう制度を見直すべきか?
- まとめ:声をあげないと変わらない
なぜ選挙後に一票の格差が話題になるのか?
選挙が終わると、「一票の格差」の問題が毎回のように注目されます。これは、選挙結果が出て初めて、
「票の価値の不平等」が実際の当選結果として可視化されるためです。
2025年参院選では、選挙区間で最大3.13倍の格差が生じ、弁護士グループが全国14の高裁・支部に「選挙無効」を求める提訴を実施しました(
TBS NEWS DIG、朝日新聞)。
また最高裁は、「一票の格差が2倍を超えると違憲状態にあたる可能性がある」と複数の判決で示しています(例:
2021年衆院選判決)。
こうした法的背景もあり、「今回の制度で本当に民意が反映されたのか?」という声が、選挙後に一気に高まるのです。
「一票の格差」の象徴としての北海道
この問題をより具体的に考えるために、象徴的な事例として取り上げたいのが北海道選挙区です。
北海道は都市と地方の要素を併せ持ち、かつ人口規模も大きいにもかかわらず、現行制度のもとでは票の価値が著しく低く抑えられている状態です。
北海道の票はなぜ「軽い」のか?
– 北海道の有権者数:約430万人(2025年時点)
– 改選議席数:3議席
→ 1議席あたり約143万人が必要になります。
一方、人口の少ない県では1議席あたり50万人未満のケースもあり、北海道の1票はその約1/3の価値しかありません。
北海道選挙区に見る制度の矛盾
北海道は、「一票の格差」や「制度の限界」を象徴する存在です:
人口が多いのに議席が少ない
札幌市など都市部を抱えていながら、議席数はわずか3。都市の声が十分に国会に届きません。
「都市」と「地方」の板挟み
北海道は都会と過疎地を同時に抱える地域。都市部としての代表も、地方としての救済も中途半端になっています。
選挙結果に不公平感が強く出やすい
2025年参院選では、3議席目をめぐって複数の野党候補に票が割れ、与党系候補が漁夫の利を得て当選。
都市部で多くの票を集めた候補が落選し、「民意が反映されていない」という不満が広がりました。
今後どう制度を見直すべきか?
| 改革案 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 広域合区制 | 小規模県を合区して定数調整 | 格差是正が進む | 地域代表が薄れる懸念 |
| 全国区制 | 都道府県制をやめて全国で比例選出 | 格差ほぼゼロに | 地元密着政治が弱まる |
| 自動定数調整制 | 定期的に人口比で定数を再配分 | 柔軟な対応可能 | 制度が複雑、地方軽視の声も |
まとめ:声をあげないと変わらない
北海道のように広大で多様な地域性を持つ選挙区でも、現行制度では「1票の軽さ」という不公平を抱えています。
これは北海道だけの問題ではなく、民主主義の根幹に関わる全国的な課題です。
「また仕方なかった」と諦める前に、どこに問題があるのかを知り、変える声をあげることが、未来の制度を築く第一歩になるはずです。
私たち親世代が政治を「自分ごと」として考えることは、きっと未来につながるはず。よかったら、こちらの記事も読んでみてください。




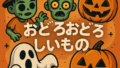
コメント